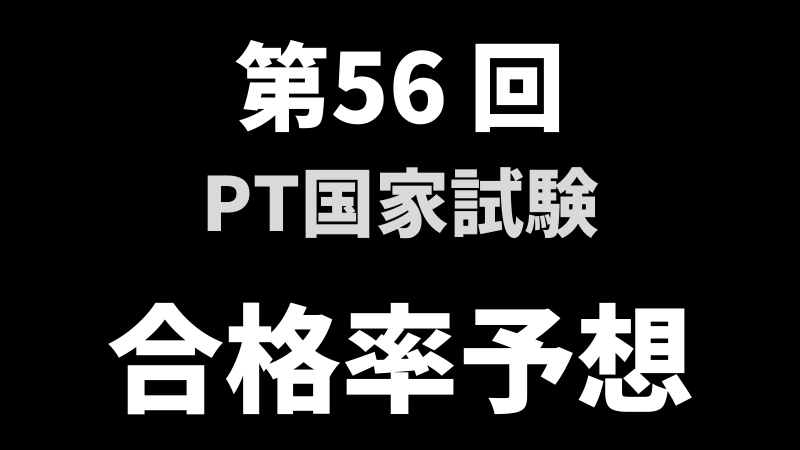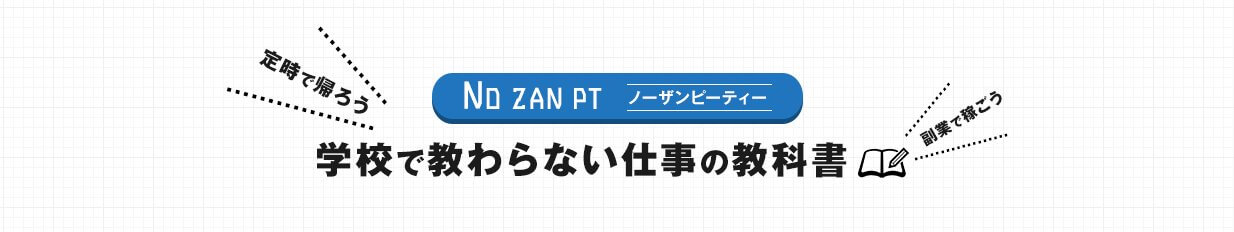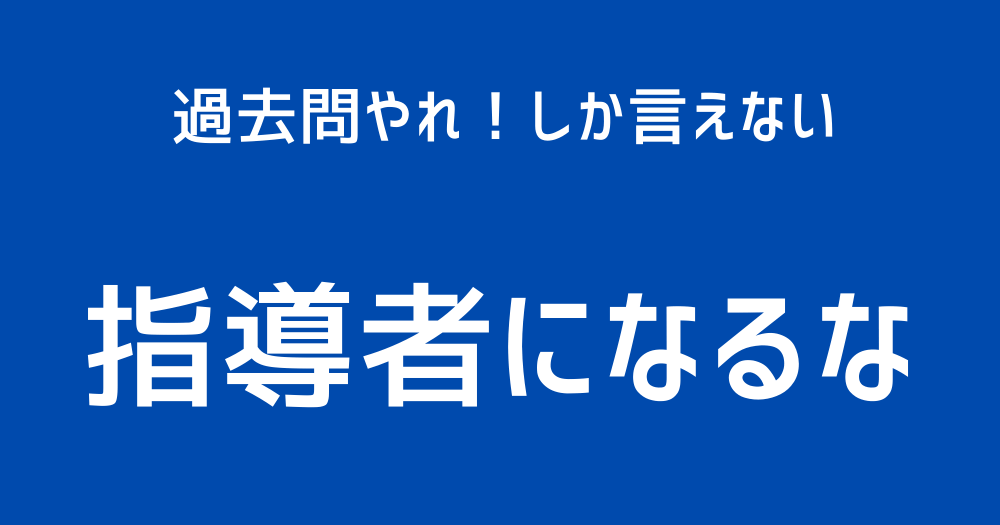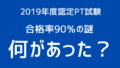理学療法学生の国家試験対策にそろそろ取り組む方も多いのではないでしょうか。
本当に合格を目指したいのであれば、2月までの半年間は人生で最も勉強すべき時期。
でも学生はそのことをあまり理解してないんですよね。
ネットでは「1か月で合格できる!」とかいろいろな情報がありますし。

でもやっぱり国試は「絶対に落としてはいけない試験」ですから、学生にはしっかり勉強してほしいもの。
しかし、肝心の指導者が国試対策を全く理解してないから困ったものです。
「過去問やっておけば大丈夫だ」という、無能な指導になっていませんか?
過去問は重要だが完璧ではない
過去問は確かに重要です。
- 出題傾向が分かる
- 分野ごとの苦手がわかる
- 実際の国家試験に慣れることが出来る
このような理由が挙げられます。
ただし、過去問はあくまで過去に出題された問題。
過去問をやったからって合格する保証は全くありません。
なぜ過去問が神格化されるのか?
なぜ指導者(学校教員も含め)は過去問をやれと口をそろえて言うのか。
その理由は「出題傾向」です。
過去問を10年分くらい解いていると、ある問題が言葉尻を変えて複数回出題されることに気づきます。
これを「類似問題」といい、選択肢や問いかけの方法を変えて出題される問題です。
ということは、次の国家試験も似たような問題が出てくると考えられるので、過去問を解いておくと類似問題に対応できるようになるんです。
と同時に、指導者は国家試験対策といえば過去問しか知らない事が多いです。
「国試対策を教えたいけど、どう教えたらいいか分からない、だからとりあえず過去問をやらせておこう」となるんです。
そもそも、指導者も「過去問をやれ」と教わってきた世代ですからね。
過去問以外でやっておくべき勉強法
それでは、過去問以外の指導方法を知らない皆さんに向けて、どんな対策を取ればいいのかをお伝えします。
模試を重要視する
過去問は国試対策の導入という意味ではかなり有効ですが、決定的な弱点があります。
それが「新規問題に全く太刀打ちできない」ということ。
最近の国家試験は、臨床現場を重視していたり、介護保険分野の範囲が広くなったりしています。
そのような新規問題に対して、病理学や疫学、保健医療分野を勉強することは必須。
そうなると、過去問のような寄せ集めした勉強だけでは合格点に届きません。
となると、対策に重要なのが「予測問題」です。
三輪書店やアイペックなどの全国模試を重点的に勉強することで、新規問題にも太刀打ちできるようになります。
教科書を使い問題集の選択肢をさらに掘り下げる
最短で合格!効率のいいみんなの勉強方法と学習時間【理学療法士国家試験対策】≫でも説明していますが、問題を解くだけでなく深堀することが重要です。
- 下腿内側 ── 伏在神経
- 母指背側 ── 正中神経
- 上腕内側 ── 橈骨神経
- 前腕尺側 ── 筋皮神経
- 足指背側 ── 脛骨神経
という問題に対し、答えは2,3,4,5で各々の神経支配は以下の通りです。
- 下腿内側 -伏在神経
- 母指背側-橈骨神経(末節部は,正中神経支配とするものもある)
- 前腕尺側-前腕内側皮神経
- 上腕内側-助間上腕皮神経と内側上腕皮神経
- 足指背側-浅・深腓骨神経
ここからさらに踏み込んでいくのがこの時期の勉強法です。
-
- 選択肢1の下腿内側の感覚神経は伏在神経ですが、その他に伏在神経支配の部位はどこかな?
- 選択肢2の母指背側の感覚神経は橈骨神経ですが、その他に橈骨神経支配の部位はどこかな?
このように、教科書を使いながら過去問の解答からドンドン掘り下げていきます。
国試対策の基本
- 過去問を解いて国試に慣れる
- 模試や問題集で新規問題に触れる
- 問題を掘り下げる
過去問や模試も、単に繰り返し解いて正答を覚えるという方法では国試に合格しません。
なぜ〇なのか?×なのかを吟味し、深堀していく事で「知っている問題なのに、間違える」ということになりません。
また、近年では出題傾向がかなり変化しています。
最新の模擬試験や問題集を活用し、新しい傾向の予測を立てておくのは非常に重要。
国試対策はメンタル教科も重要
- 分からない問題は飛ばす
- たった6割取れれば合格なんだから余裕
- 自分ルールを決めさせる
- 本番の休憩時間で答え合わせをしない
国試対策はメンタルとの戦いでもあります。
ある程度の心構えは指導しておいてください。
- 国試は時間が限られているので、分からない問題は悩まず飛ばす。
- わからなければ「アを選ぶ」などの自分ルールを作らせる
などの対応は必須です。
また、国試は60%取れれば100%合格するという話をして学生の負担を軽減させてあげる事。
本番中に答え合わせをして一喜一憂しても無駄なので、休憩時間中は午後のテストに向けて対策するなどの攻略法を教えるのもおすすめです。
2020年度の国家試験の予想はこちら
指導の参考にしてください。