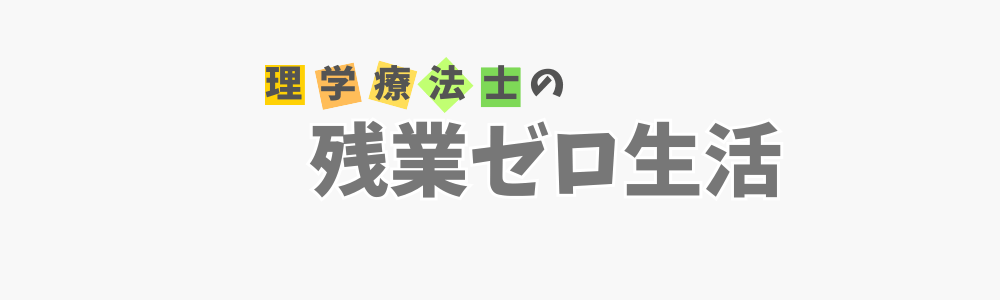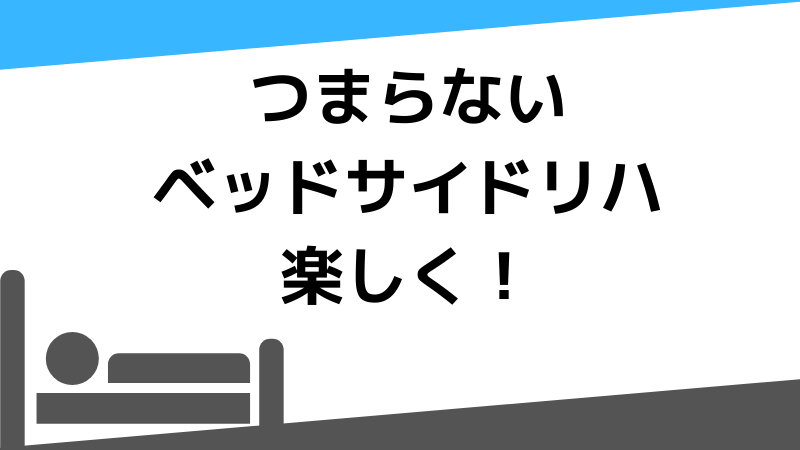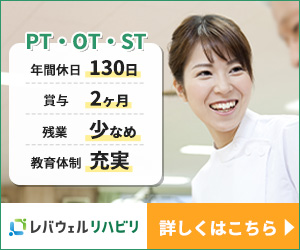「寝たきりで動けないのにリハビリをする必要はあるの?」
理学療法士として病院で働いているなら、1度はそう思ったこともあるのではないでしょうか?
絶対に良くならない重症疾患や、高齢で食事も取れないような寝たきりの患者さん。
我々は色々な方のリハビリを実施します。
そんな患者を目の前にして「この人へのリハビリって・・・何をしたらいいんだろう?」と考え込んでしまう事ってありませんか?
特に病院で働いて間もない新入職員は目の前の重症患者に対して効果的な治療法を立案できず「私はこの仕事に向いていない」なんて悩んでしまうことも。
寝たきりの患者へのベッドサイドリハが毎日続くと、「このリハビリの意味はあるのだろうか?」と考えてしまうのも無理はありません。
そんなあなたに、寝たきりや重症患者に対するリハビリの方法、考え方をお伝えします。
寝たきりのリハビリのやり方と基本的アプローチ
寝たきり患者に対するリハビリでまず考えなければならないのは「改善」でなく「維持」です。
自分で動けない患者は生命維持・身体コントロールができないので理学療法士が患者の生命維持に対してどんなアプローチが必要か考えるべきです。
- 褥瘡予防の体交
- ポジショニング
- 拘縮予防の可動域練習
- ギャッチアップでの脳血流量確保
- 離床
- 姿勢反射促し
- 喀痰
いろいろ考えるべきことはあります。
寝たきりで意識が無いからリハビリはしなくてもいい、というのは全くの間違い。
他部門との連携
寝たきり患者に対するアプローチは、理学療法士の力だけで対応するのは不可能です。
医師を始めとした看護師や作業療法士、介護士などのコメディカルにもきちんとコミュニケーションをとり、情報共有していく必要があります。
- 褥瘡予防のポジショニングの共有
- 体位交換のタイミングや清拭時の骨折リスクなどの共有
- 看護師や家族に他動ROMの方法の共有
- 体交方法の共有
- 喀痰・吸引のタイミングの共有
こう言った事を専門的知識から考え、情報共有していくべきです。
寝たきりのリハビリのマッサージ
皮膚に直接刺激を与えることで、血液循環をよくして代謝を促進する目的があります。
身体機能の改善を促すように、全身や各局所をさすります。
関節可動域の拡大、血液やリンパの循環を良くする効果が期待できます。
基本的には大きな筋肉から実施し、末梢から中枢に向けてマッサージしていきます。
ストレッチ
柔軟性の向上・痛みの改善・運動機能の向上を目的とします。
寝たきりでは、筋肉は硬くなってしまうので、マッサージで筋肉の緊張をとり血行を促進させます。
筋緊張が落ちれば、可動域も上がりますし、拘縮の予防にもつながります。
筋力トレーニング
寝たきりでも、動かせる筋肉を使う筋トレを行います。
特に握力は比較的後期まで保たれるので、手のひらでグーパーをしたり、足の指を開いたり閉じたりする運動でも十分な効果をもたらします。
それぞれ10回を1セットとし、じっくり、ゆっくり運動をしていきます。
廃用症候群を予防し、筋力を維持させることで起き上がる際の強力動作などに繋げていきます。
寝たきりのリハビリで意識すること
端座位練習
寝たきりの状態が長いと、循環器系の低下につながります。
ギャッチアップでもいいのですが、ベッド上で端座位姿勢をさせてみましょう。
座る姿勢をキープするだけでも筋肉は使われますし、心臓より頭部が上になるので脳血流量の向上にもつながります。
バランス能力の向上も期待できるうえに、床ずれ予防にもつながります。
車いすに座れるのであれば、積極的な離床を促し、無理のない範囲で端坐位練習をしてみましょう。
褥瘡予防
同じ体勢のまま長時間寝ていると、骨の突出部分などが圧迫され、褥瘡になってしまいます。
褥瘡が重症化すると、筋膜や骨にまで達してしまいます。
「体位変換」「体圧分散用具」「ポジショニング」など正しいケアを提案するのも理学療法士の仕事です。
皮膚の清潔
寝たきりでは、入浴や着替えの頻度が減少します。
皮膚を清潔に保たないと、血液循環の圧巻、褥瘡や拘縮のリスクにつながります。
皮膚の状態をチェックして、身体異常に気が付くようにしてください。
手浴や足浴など、部分的な清拭でもOKです。
患者がリラックスできるように、室温調整やプライバシーにも注意をして行います。
寝たきり患者のリハビリでモチベーションを保つのは難しい
寝たきり患者に対するリハビリはかなり重要で、リハビリ次第では動きが出たりコミュニケーションが取れたりといった回復を見せることも多いです。
しかし、急性期病院のように「患者がみるみる良くなっていく」ようなことや、回復期病院のように「ADLが自立し、笑顔で握手をして退院していった」というようなことにはなりません。
毎日のわずかな変化でモチベーションを保っていくのは正直難しいですし、そういった仕事が合わない方も居ます。
もちろん、亡くなる場面に遭遇したり、重度の認知症で理不尽な暴言を吐かれたりすることもあります。
そういう日々が続くと「この仕事向いてない・・・」と思ってしまうことも。
でも待ってください、あなたが向いてないのは「いまの職場」であり「理学療法士」ではありません。
寝たきり患者のリハビリが苦痛でやりがいが見つからなかったら、もっとアクティブに動ける方がいる病院に勤めればいいだけかもしれません。
例えば、整形外科クリニックなどの外来リハビリテーションであれば、患者は基本的に自立しています。
主訴の多くは「痛み」であり、運動方法も多彩でスポーツ系の方も多く、かなりアクティブな治療を実施することができます。

また、回復期リハビリを実施している病院もおすすめ。
回復期リハビリ病院に来る方は基本的に「リハビリをしたい、良くなりたい」と思っている方が多いのでリハビリに積極的です。
ADLもガンガン上げていけますし、日々変化していく世数を見るのは非常に面白いです。
このように、いまの職場が「つまらない、面白くない」と感じているのであれば、無理にその職場でやりがいを見つける必要はなく、職場を変えてしまうのも1つの手段。
そんなことを言うと怒られてしまうかもしれませんが、実際に治療者が楽しい、やりがいがある!と感じていなければ良質なリハビリを提供するのは不可能です。
もちろん、外来も回復期もそれなりに大変なことが多いです。
でもそれを「大変」と思うか「楽しい」と思うかは、働く人次第だと思うんですよね。
どうせなら「楽しい」と思える職場で働いたほうがいいじゃないですか。
もしも、寝たきり患者のリハビリにやりがいを見いだせず悩んでいるのであれば、ぜひ外来や回復期の職場を見学しに行ってみてください。
あなたにハマるかもしれませんし、そこから飛躍的に成長する可能性もありますから。