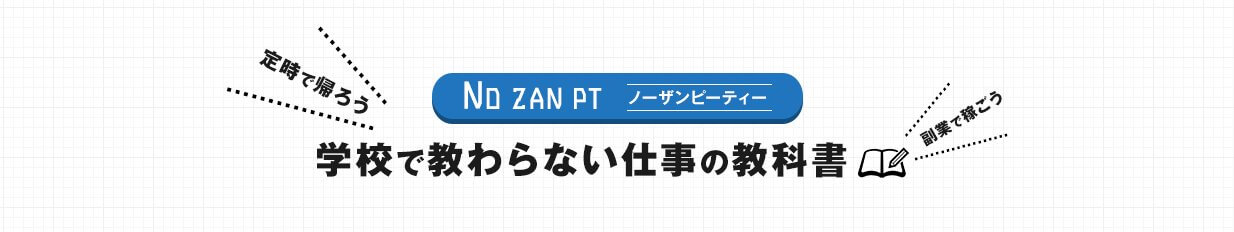小児リハビリでは運動発達という分野があり、リハビリでは子供の運動状況を見て、発達に遅れがあるのか?異常はないか?を常に評価しています。
- うちの子は遅れてるのかな?
- まだしゃべらないけど大丈夫かな?
親はメチャクチャ不安ですよね。
ここでは、一般的な発達段階を月齢ごとに並べて、どんなことができるかをお伝えしていきます。
勘違いしないでいただきたいのは、ここに載っていることができないからといって発達遅滞ではないということ。
子供の成長は差があって当たり前。
少々のずれは気にしないでいいと思います。
うちの姪っ子も、全然言葉が離せませんでしたが今は全く問題なく学校に通っています。
ただし、1年以上ズレている、なんか日常生活でおかしなところがあるといった場合は専門医に診てもらうことをおすすめします。
今は行政で発達段階を検査することもしているので、気になったら各自治体(市役所など)にご連絡をどうぞ。
乳児期(1~11か月)の発達段階

1~12か月(1歳)までは急激にできることが増えていきます。
その分、誤差も生じやすいので、多少遅れたり早くてもそこまで心配しなくても大丈夫です。
【1か月】
- 振れたものを握る

0~1か月くらい
【2か月】
- あやすと笑う
【3か月】
- 首がすわる
- ガラガラを握る
【4か月】
- ガラガラを振り回す
- 両手で持つ
- いないいないばぁを喜ぶ
- スプーンから飲める
【5か月】
- 寝返りをうつ
- 自発的に掴む
- 赤ちゃん言葉を話す
- ビスケットを自分で持つ
【6か月・7か月】
- 支えなしで座る
- 持ち替える
- 人見知りをする

7か月くらい
【8か月】
- ハイハイをする
- 両手の積み木を打ち合わせる
【9か月】
- 掴まり立ち
- バイバイをする
【10か月】
- 伝い歩き
- 箱の中に物を出し入れ
- 親指と人差し指でつまむ
- 大人の動作の真似をする
【11か月】
- 1人で歩く
- なぐり書きをする
- ママ、パパと言う
- 指さし
- 自分でコップで飲む

11か月くらい
幼児期(12~23か月)の発達段階
【12~14か月:1歳~1歳2か月】
- 道具の使い方が分かる
- 意味のない言葉を連続して言う
- スプーンを使う
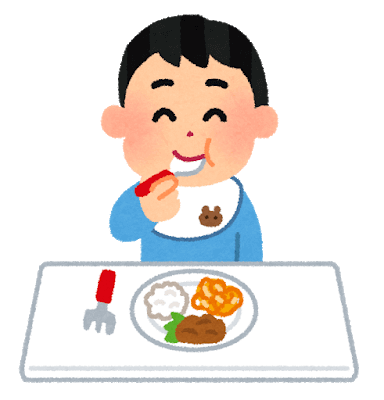
1歳くらい
【15~17か月:1歳3か月~1歳5か月】
- 3個の積み木を積む
- 〇・×・△がわかる
【18か月:1歳半】
- ボールをける
【19か月:1歳7か月】
- 見たてあそび
【20か月:1歳8か月】
- ボールを上手投げする
- 名前を呼ばれて返事をする
- 簡単な東京問いかけに言葉で答える
- 靴を脱ぐ
【21・22か月:1歳9か月~1歳10か月】
- 2語文を話す
【23か月:1歳11か月】
- その場でジャンプ
幼児期(24~35か月)の発達段階

【24か月~26か月:2歳~2歳2か月】
- トイレトレーニングができる
- 靴を履く

2歳くらい
【27か月~29か月:2歳3か月~2歳5か月】
- 姓名を言う
【30か月:2歳半】
- 掴まらずに階段昇降
- 〇を書く
- はさみで切る
- ごっこ遊び
- 大小が分かる
【31か月:2歳7か月】
- ボタン掛け
【32か月:2歳8か月】
- 顔のような絵を書く
- 色の識別ができる
【33か月~35か月:2歳9か月~2歳11か月】
- 積み木でトンネル等を作れる
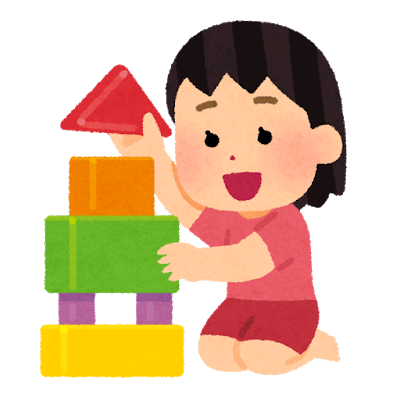
2歳10か月くらい
幼児期(36~72か月)の発達段階
【36か月~42か月:3歳~3歳半】
- 三輪車が漕げる
- 会話が上手にできる
- 数を理解し、3まで数える
- 自分で洋服を着る
- 1人でトイレに行く
- お手伝いができる
- 箸を使う
- 片脚ケンケン
【42か月~48か月:3歳半~4歳】
- でんぐり返し
- 口をすすぐ
- お風呂で自分の体を洗う
【48か月~54か月:4歳~4歳半】
- 数を理解して10まで数える
【54か月~60か月:4歳半~5歳】
- スキップ
- はさみで形を切り抜く
- 文字を読む
- トイレの始末ができる
【60か月~72か月:5歳~6歳】
- 補助輪付き自転車に乗る
- 思った絵を書く
- 折り紙で飛行機を折る
- 時間が分かり始める

5~6歳くらい
【参考|子どもの発達・発育 目安表:社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会】
乳幼児の発達は周囲環境に影響を受けます
0~6歳までの乳幼児の発達は、周囲環境によってかなり変化を受けます。
危ないからといって、親が先回りして危険回避ばかりしていると、子供は学習する機会を失ってしまい発達段階が遅れたりします。
ぼくの友人の子供は、三輪車を後ろからずっと押して散歩していたら5歳になっても「漕ぐ」という運動ができませんでした。
これを「発達遅滞か?」というとそうじゃないですよね。
過保護な親のせいです。
発達は本当に理解したり判断したりするのが難しいのですが、その子の生活環境にもフォーカスしていかないと正確な判断はできません。
親になった皆さんも、あまり過保護にせず伸び伸びと過ごしていくことが、正常な発達を促せるのではないかと思います。