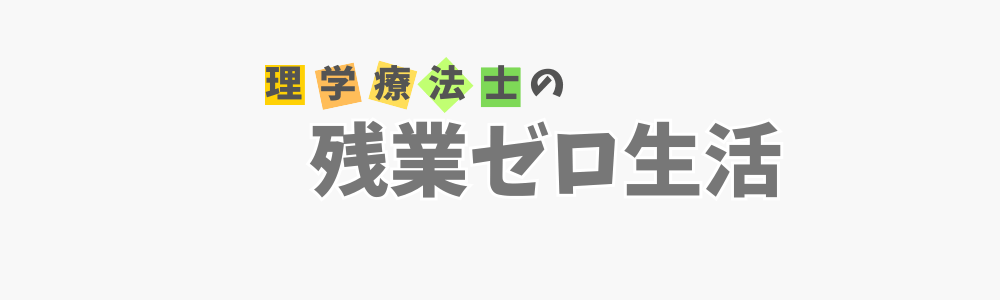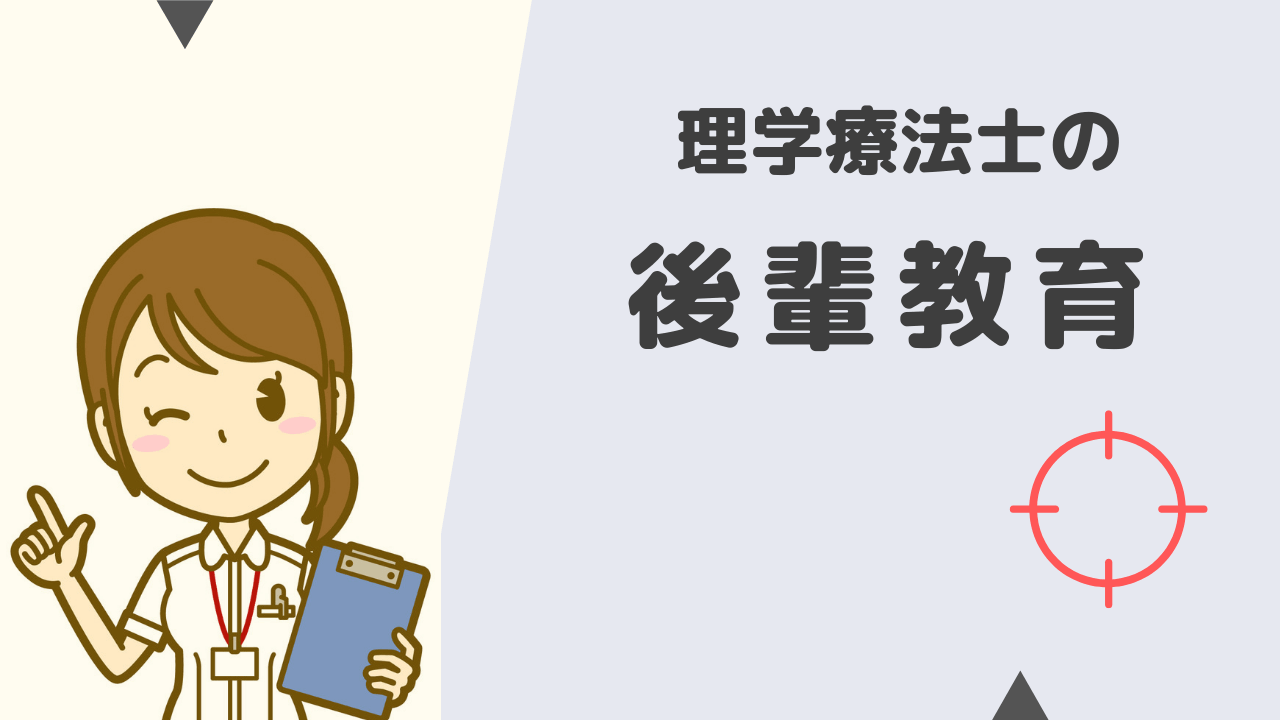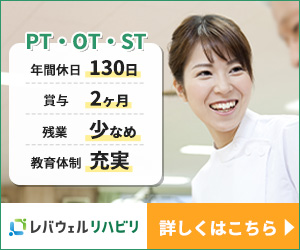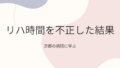科学的根拠に基づいた医療を実践できること。また、良質な医療従事者を提供するための教育の実施。
理学療法士はただ単にリハビリをして患者の身体機能を向上させるだけが目的ではありません。
- 治療効果を論文などの報告から紐解き、自ら検証することができること
- 医療研究を通して、その活動を積極的に提供し発信できること
- 特定の手技や知識にとらわれず、幅広い視野の発想ができること
- 患者に適した課題や難易度のレベルを決定できること
- 後輩や学生の教育、指導ができること
- 他職種や他部門と協力し、一つのゴールに進むことができること
教育を施して目指すべき理学療法士の姿が上記のものになります。
教育をする側も、される側もこれら7つの課題を念頭に置き、良質な医療従事者となるべく努力していく必要があります。
理学療法士の育成機関
理学療法士の育成機関は大学(短期大学も含む)と専門学校が主です。
専門のカリキュラムを最低でも3年間の間に指定単位数取得しなければ理学療法士の国家試験を受講することはできません。
大学と専門学校の違いにも注目する必要があります。
大学
大学の特徴の1つとして、理学療法士の専門授業の他に一般教養の授業があることです。
大学によっては英語や中国語の授業があることも。
また、大学を卒業することで「学位」が与えられるので大学院に行ってさらなる高みを目指すことも可能です。
専門学校
専門学校の特徴として、3年間のカリキュラムで良い学校もあり、大学より1年早く現場に出れるというところです。
短期間でみっちりと専門職の勉強をしますので、現場での戦力にはなりやすいと言えるかもしれません。
理学療法士に絶対なる!という高い志の人が集まるので、一緒に切磋琢磨していくこともできるでしょう。また、治療器具などの設備も、専門学校は優れている場合が多いです。
大学と専門学校での給料の違い
特に差はありません。
大卒も専門卒も、リハビリ介入による点数(病院への収入)は変わらないので、給料も変わりません。
しかし、一部の病院では5000~10000円程度、大学卒のほうが高い場合があるようです。
養成校一覧
養成校の費用
理学療法士になるためにはかなりのお金がかかります。
以前よりは安くなったと思うのですが、100万や200万では足りません。
それに見合ったカリキュラムが組まれていますし、理学療法士になったとすればその学費分以上の恩恵は受けられると思います。
- 国立大学:約242万円/4年間
- 私立大学:約500~700万円/4年間
- 専門学校(4年):約500~700万円/4年間
- 専門学校(3年):約350~500万円/3年間
詳しくはこちら>>>
理学療法士になるにはいくらかかる?学校による必要な学費の差
理学療法士の試験
理学療法士になるには毎年2月に行われる国家試験で167点/280点満点以上取ることが必要です。
一般問題
1問1点で160点満点です。
【一般問題の出題範囲】
- 解剖学
- 生理学
- 運動学
- 病理学概論
- 臨床心理学
- リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)
- 臨床医学大要(人間発達学を含む。)
- 理学療法
実地問題
1問3点で120点満点です。
この実地問題で43点以上取れていないと、いくら点数が高くても不合格になります。
【合格基準】
-
280点の内168点以上
-
かつ、実地問題で43点以上(11問以上)
【実地問題の出題範囲】
- 運動学
- 臨床心理学
- リハビリテーション医学
- 臨床医学大要(人間発達学を含む。)
- 理学療法
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第11条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成31年3月15日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
- 外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の免許に相当する免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 法施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、理学療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業した者
【引用|厚生労働省】
勉強方法
試験は5択のマークシートですが、カンで正解できるほど甘いものではありません。
勉強法も様々なので、自分に合った方法を見つけ出してください。
詳しくはこちら>>>
理学療法士国家試験に向けた勉強の方法!
解答速報
解答速報は様々なサイトで試験当日に出回ります。
当サイトでも、試験当日の夜9時~12時くらいにかけて解答速報を提示しています。
2020年解答速報はこちら>>>
※準備中
合格発表
合格発表は3月に行われます。
インターネットや、合格発表会場で確認することができます。
詳しくはこちら>>>
国家試験の合格発表を『最速でストレスなく』確認する方法
理学療法士の実習
理学療法士になるために避けて通れないのが臨床実習です。
実習を通して、現場の考え方や雰囲気を掴み、より実践に近い環境で学んでいくことが目的となります。
臨床実習ではクリニカルリーズニングに基づいた考えを展開し、より専門的かつ理学療法士として適切な行動や態度を修得することが目的です。
詳しくはこちら>>>
臨床実習の目的
- 養成校で学んだ知識・技術を臨床現場で実用すること
- 専門職として求められる行動・態度・責任感を修得すること
- 対象の訴えや症状から病態を推測し、仮設に基づき最も適した介入を決定していく経験をすること
見学実習
養成校で学習した内容を臨床現場に落とし込み、確認、理解していく過程。
この実習では、理学療法士としての仕事の全体像をつかむことに重きを置くため、病態理解や統合と解釈などは行われないことが多いです。
検査・測定した結果の意義や意味を考え、社会人として節度ある態度や話し方を体験することも重要なプログラムの位置づけとされています。
評価実習
養成校で学んだ評価技術、医学知識を活用し評価測定結果からトップダウン方式で問題点を抽出していく過程を経験します。
養成校で学んだ技術や知識を現場レベルで活用するための困難さに四苦八苦することも多く、学生生活の1つの大きな壁となります。
しかし、そのような体験も重要なプログラムであると認識しています。
また、患者やセラピストとの良好な関係性を作る(信頼関係の構築)ことも重要視されます。
治療実習
養成校で学んだ知識・技術をすべて総動員し、対象者の問題点抽出からプロラム作成および治療の実施までを行います。
実際に一連の流れを経験することで専門職としての自信・責任感を構築していくことが主な目的となります。
治療を実施し、そこから再評価を繰り返す体験をし、より臨床家として高い水準を目指していきます。
クリニカルクラークシップ
クリニカルクラークシップ(clinical clerkship)は、従来の見学型臨床実習とは異なり、学生が医療チームの一員として実際の診療に参加し、担当セラピストと共同で臨床に取り組むより実践的な実習モデルです。
学生も臨床に参加し、指導者の監視の下で一定の範囲内での医行為を実践していきます。
それにより学生は、自らの主体性と責任感をもって学ぶことができます。
詳しく見る>>>
理学療法士の臨床デビュー
理学療法士として現場に出ると、養成校で学んだことが役に立たないことが多いんです。
養成校は、あくまで『国家試験に合格する能力を養う場所』という感じなので、実際に臨床現場に出ると(実習を経験してきたとはいえ)全く思うように治療ができない場面が多く出てきます。
そんな臨床現場で少しでも役に立てるよう、基礎的な『現場レベル』の知識を得られることが目的となります。
詳しくはこちら>>>
評価
理学療法の基本は『評価』です。
評価が出来なければ治療は出来ませんし、治療ができる人は必ず評価が出来ています。
ROMやMMTなどの基本的な評価の方法ではなく、実際に臨床現場で使える実用的な評価の方法をまとめてあります。
治療
『治療』といっても様々。
器質的な問題を排除することで改善させていく治療の他に、残存能力を使った動作の改善を図る治療や、環境整備によって動きやすくするための治療など多岐にわたります。
臨床レベルでの目的は『患者や家族のホープを叶えること』となります。
しっかりとゴール設定を立て、どのような治療プログラムを実施していけばいいのかをまとめています。
臨床スキル
『評価技術』『治療技術』だけでは理学療法士として働いていけません。
臨床で活躍するためにはそれ以外のスキルが必要となります。
信頼関係の築き方、情報の引き出し方、他部門との連携など臨床で役立つスキルについてまとめています。
理学療法士が重要視しておきたいこと
理学療法士としてこれから活躍していこうと考えているのであれば
- PDCAサイクル
- 業務改善
- ビジネスマナー
- 安全管理
は必須。
これができていない理学療法士は淘汰されたり、選ばれなくなったりしていきます。
デキる理学療法士になるためにぜひ押さえておきたい項目です。
詳しくはこちら>>>
PDCAサイクル
PDCAサイクルとは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)の 4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する手段。
日々の業務や治療法に対しPDCAを回すことで毎日成長していきます。
成長のない理学療法士は後輩にどんどん追い抜かれていき、最終的に選ばれなくなっていくことでしょう。
【簡単理解】PDCAサイクルの回し方を詳しく見る>>>
業務改善
日々の仕事に対する改善を図り、効率のいい仕事をしていくことが業務改善の本質になります。
効率的に仕事をこなすことで余暇時間を作り出し、定時退社やアフター5、家族との時間などに割り当てることを目的とします。
無駄な仕事が多い理学療法士は、自らの社会的価値を下げているにほかなりません。
同じ給料しか貰えないのであれば、パパッと仕事を終わらせて自分の時間に使ったほうが有益なことは言うまでもありませんね。
【簡単理解】業務改善の方法を詳しく見る>>>
ビジネスマナー
理学療法士は『接客業』です。
患者や、患者家族、社会福祉を相手にするビジネスだととらえれば、ビジネスマナーの有用性は理解できるはず。
ビジネスマナーは理学療法士のみならず、社会人として抑えておきたいスキルのひとつです。
理学療法士に重要なビジネスマナーを詳しく見る>>>
安全管理
患者を相手に仕事をする以上、安全管理には最新の注意を払わなければなりません。
リハビリは危険なこともしなければならない事も多く、安全管理を怠ると重大な事故になりかねません。
安全管理の方法や注意点、インシデントやアクシデントについてお話しています。
【超重要!】!理学療法士と安全管理を詳しく見る>>>