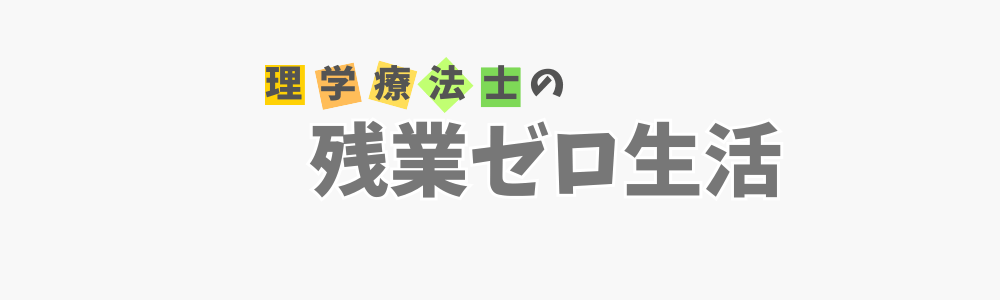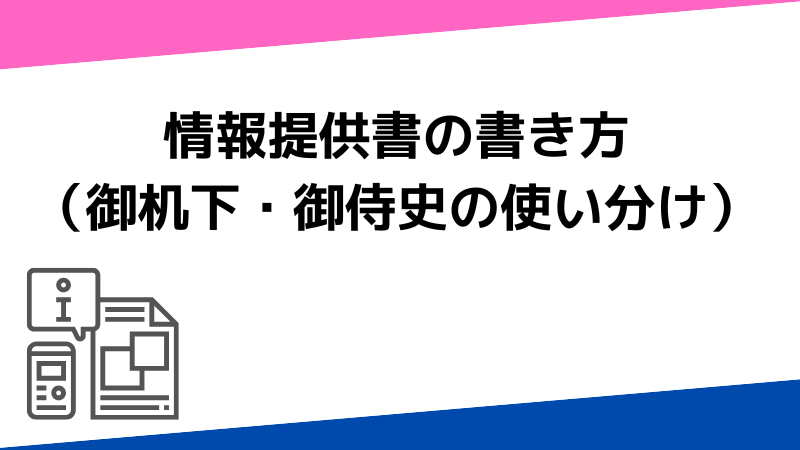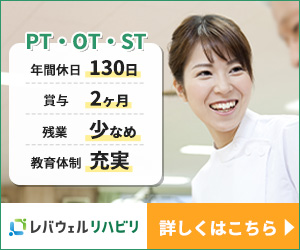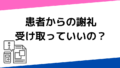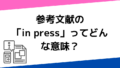「情報提供書書いてください」って急に言われると、正直ちょっと困りますよね。
「え、何書けばいいの?」
「どこまで詳しく?」
みたいに悩む人も多いはず。
でもポイントを押さえれば、そこまで難しくありません。
今回はリハビリ情報提供書の書き方をわかりやすく解説していきます!
リハビリ情報提供書の書き方何を書けばいいの?
リハビリ情報提供書の書き方の基本は「次につなげる情報」です。
つまり、これから関わる医師やリハビリスタッフ、施設の職員さんに「この人はこんな状況で、こんなリハビリやってきましたよ」と伝えるためのもの。
余計なことは書かなくてOKですが、必要なことは漏れなく書きましょう。
経過
ざっくりでいいので、ここまでのリハビリの流れを書きます。
- どんな疾患やケガで入院/通院したのか
- どのくらいの期間リハビリをしてきたのか
- 大きな変化(歩けるようになった!杖が不要になった!など)
入院時や初期評価時の状況
最初の状態を書いておくと、リハビリの成果や進み具合が伝わりやすいです。
- どこに障害があったか
- どのくらい日常生活に支障があったか
- ADL(食事・排泄・入浴など)レベル
治療方針やゴールを記載
リハビリってゴール設定が超大事。
「歩行自立を目指した」とか「在宅復帰に向けてADL向上を目的にした」とか、リハビリの方向性をしっかり書いておきましょう。
患者の性格
意外と忘れがちだけど、これ大事です!
性格を一言添えるだけで、次のスタッフが「どう関わったらうまくいくか」のヒントになります。
最終評価結果を記載
最後に「今どんな状態か」をまとめます。
- 歩行レベル(独歩・杖歩行・車いすなど)
- ADLの自立度
- 認知機能やコミュニケーションの状態
リハビリ情報提供書の宛名は?
情報提供書の宛名は、基本的に「〇〇先生」や「〇〇病院 リハビリテーション科 御中」といった形。
そのほかにも、御机下(おんきか)や、御侍史(ごじし)と書く場合もあります。
「御机下(おんきか)」とは
相手(先生本人)に直接渡すのは恐れ多いので、机の下に置かせていただきます、というニュアンス。
医師、教授、弁護士など 個人宛に使う。
〇〇病院 整形外科△△ 先生 御机下
「御侍史(ごじし)」とは
直接渡すのは控えて、秘書やお弟子さんを通じてお渡しするニュアンス。
こちらも 医師や教授など個人宛に使える。
〇〇病院 整形外科△△ 先生 御侍史
使い分けのイメージ
- 御机下:机の下に置かせていただきます → 先生本人宛
- 御侍史:お付きの方を通じて渡します → 先生+秘書などを想定
どちらを使っても大きな間違いではありませんが、最近は 御侍史の方がよく使われる ことが多いです。
もし「リハビリ情報提供書」に書くなら、
- 個人の先生宛 → 「御机下」or「御侍史」
- 病院や部署宛 → 「御中」
で使い分けるとバッチリです!
送付先の相手の職種を考えよう
送る相手によって、強調するポイントを変えるのもコツです。
- 医師 → 医学的な経過や診断名、治療方針のまとめ
- PT/OT/ST → 機能評価やADLの細かいデータ
- ケアマネ → 日常生活にどこまで支援が必要か
例文サンプル
以下はあくまでイメージ用のサンプルです。
実際に書くときは、施設や病院のフォーマットに合わせてくださいね。
宛名
〇〇病院 リハビリテーション科 御中患者氏名
山田 太郎 様(78歳・男性)診断名
右大腿骨頸部骨折 術後経過
2025年6月に転倒し、右大腿骨頸部骨折を受傷。観血的整復固定術を施行後、当院にてリハビリ開始。術後早期より歩行練習を行い、約2か月間の入院リハビリを実施した。入院時の状態(初期評価)
移動:ベッドから車椅子移乗は全介助
歩行:不可
ADL:食事は自立、排泄・入浴は全介助
認知機能:軽度低下あり(短期記憶にやや不安)
治療方針・ゴール
歩行器使用での自立歩行を目標
トイレ動作の自立
在宅復帰を最終目標に設定
リハビリ経過
2週目より平行棒内での立位・歩行練習開始
4週目より歩行器で20m歩行可能
6週目にはトイレ動作が一部自立
患者の性格
積極的で練習にも前向き
不安が強い場面では声かけで落ち着く傾向あり
最終評価(退院時)
歩行:歩行器使用で50m自立、杖歩行は監視レベル
ADL:食事・排泄自立、入浴は部分介助
認知機能:日常会話レベルは良好
備考
在宅復帰予定。環境整備(段差解消、手すり設置)が必要と考えられる。今後は外来リハビリにて歩行安定性の向上を目的とした継続訓練が望ましい。
まとめ
リハビリ情報提供書は、「ただの書類」じゃなくて、その人の人生を次につなげる大事なバトン。
書くポイントは以下の8つ。
これを意識すれば、読みやすくて役立つ情報提供書がサクッと書けるはずです。