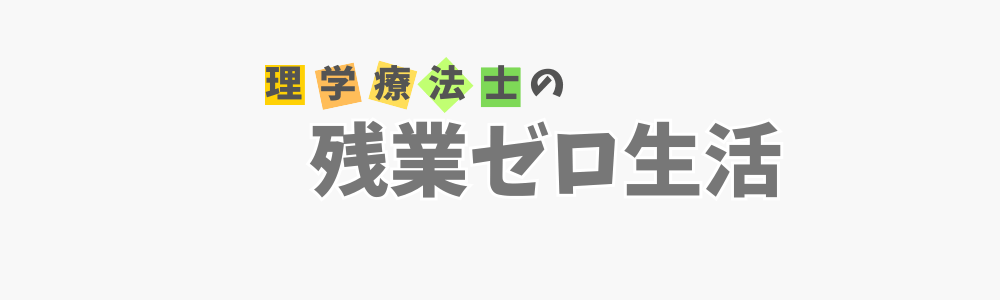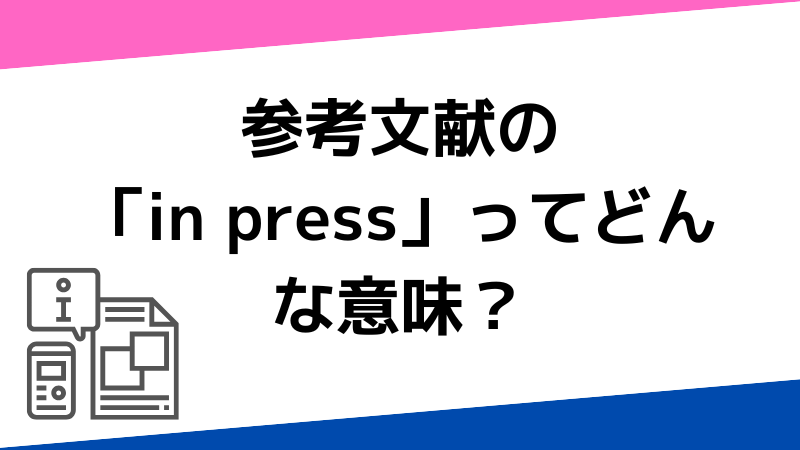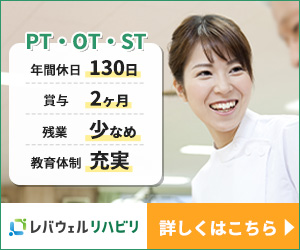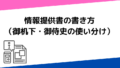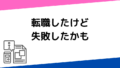論文やレポートを読んでいると、参考文献の欄にちょっと不思議な表記を見かけることがあります。
例えば「in press」とか「submitted」とか。
初めて目にすると「これってまだ論文じゃないのに引用していいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
これらは、論文の「出版までの流れ」を示す言葉で、研究成果がどの段階にあるのかを表しています。
研究論文は、研究者が原稿を書き、学術誌に投稿してから審査を受け、修正を経て、ようやく正式に出版されます。
その過程は数か月から数年かかることも珍しくありません。
つまり、研究成果がすぐに世の中に出るわけではなく、「途中段階」が存在するわけです。
その段階を示すのが「submitted」「in press」「in preparation」などの表記です。
また、まだ印刷されていない論文や、査読中の論文であっても、重要な情報源である場合は参考文献に含められます。
さらに「personal communication」のように、正式な出版物ではないけれども、研究の根拠となる場合に引用するスタイルもあるのです。
これらの言葉を知っておくと、論文リストを見るときに「これはどのくらい信頼できる情報か」を判断する手助けになります。
研究の世界では、情報の鮮度と信頼性のバランスを見極めることがとても大切。
次の項目から、それぞれの用語をわかりやすく解説していきましょう。
「in press」の意味
「in press」とは、直訳すると「印刷中」という意味です。
研究論文の場合は「すでに学術誌で採択され、正式に出版が決まっているが、まだ紙面やオンラインで公開されていない状態」を指します。
つまり、審査(査読)を無事に通過し、内容の信頼性は保証されている段階です。
この状態の論文は、すでにジャーナルによって受理されているので「正式な研究成果」として扱うことができます。
ですから、他の研究者も安心して引用することができます。
実際、多くの学術誌では、in press の段階の論文を「先取り」して引用することを認めています。
例えば、参考文献リストに
とあれば、「この論文はもう発表が決まっていて、近日中に公開されるんだな」と理解すればOKです。
研究者にとって「in press」の肩書きは非常に重要です。
なぜなら「査読を通過した実績」として評価され、就職や昇進、研究費の獲得にプラスに働くからです。
論文がまだ世に出ていなくても「受理された」という事実そのものが、研究の確かさを示す証拠になります。
つまり、「in press」は「信頼性は十分あるが、まだ一般には読めない」状態。
研究の世界では、完成に最も近いゴール直前の段階だといえます。
「submitted」の意味
「submitted」とは「投稿済み」という意味です。
これは、研究者が学術誌に論文を提出した段階を指します。
まだ編集者や査読者による審査が行われていない場合や、審査中で結論が出ていない場合に使われます。
この段階の論文は「公式には未承認」。
つまり、内容の正確さや妥当性が保証されているわけではありません。
あくまで「研究者が自信を持って投稿した原稿」という位置づけです。
そのため、多くの学術誌や学会では、submitted の段階の論文を正式な参考文献として扱うことはできません。
とはいえ、研究現場では「速報性」が求められることもあります。
特に医学や工学の分野では、新しい知見をできるだけ早く共有することが重要です。
そうした背景から「preprint(プレプリント)」として公開されることも増えてきました。
これは、査読前の submitted 論文を誰でも閲覧できるようにしたもので、近年は信頼度も徐々に上がっています。
例えば参考文献に
とあれば、「この論文は投稿中で、まだ承認されていない」と理解する必要があります。
つまり「submitted」は、言うなれば「就職の応募書類を出した状態」に近いもの。
採用されるかどうかはまだわからないけれど、研究者の挑戦は始まっているという段階なのです。
「in preparation」の意味
「in preparation」とは「準備中」という意味。
つまり、まだ学術誌に投稿すらされていない段階を指します。
研究者が原稿を書いている最中だったり、データ整理をしているところだったり、形はさまざまですが、とにかく「論文として世に出る前の状態」です。
この段階の研究は、まだ査読はもちろん、投稿すらされていないので、信頼性を保証することはできません。
そのため、基本的に正式な参考文献として引用することは認められていません。
もし文献リストに in preparation と書いてあったら、それは「将来的に論文として発表予定だけど、今はまだ未完成」という意味合いで受け取るといいでしょう。
ただし、研究仲間の間では「いま準備中の研究内容」を伝えることは珍しくありません。
学会のポスター発表や、研究室内での進捗報告などで、in preparation の内容に触れることはよくあります。
例えば参考文献に
と書かれていたら、それは「この研究はまだ発表前で、信頼できる形では世に出ていない」と考えるのが適切です。
つまり「in preparation」は、「まだ下書き段階」。完成には至っていないけれど、研究の芽が確かに存在している、そんな状態を示す表現なのです。
「personal communication」の意味
「personal communication」とは「個人的なやり取りによる情報提供」という意味です。
例えば、研究者同士がメールでやり取りした内容や、会議・口頭で聞いた話がこれにあたります。
学術誌の参考文献には、本来「誰でも確認できる情報源」を載せることが求められます。
しかし、時には「まだ公開されていないが重要な情報」が必要になることがあります。
そんなときに登場するのが「personal communication」です。
例えば、著名な研究者から直接得たデータや、まだ発表されていない知見などを
として引用します。
これは「この情報は公開されていないけれど、特定の人物から直接得ましたよ」という証拠を示すものです。
ただし、personal communication は裏付けがとれないため、慎重に扱う必要があります。
読者がその情報を確認することはできないからです。
そのため、多くの学術誌では personal communication の使用を最小限にするよう推奨しています。
つまり「personal communication」は「信頼できる専門家の口頭証言」のようなもの。
参考にはなるけれど、誰もが検証できる形ではないため、引用する場合は注意が必要です。
まとめ:5つの用語の信頼度比較
論文リストに出てくる「in press」「submitted」「in preparation」「personal communication」などは、研究の進捗や情報の確かさを示しています。
では、それぞれの信頼度はどのくらい違うのでしょうか?以下の表に整理しました。
| 用語 | 意味 | 公開状況 | 信頼度 | 参考文献での扱い |
|---|---|---|---|---|
| in press | 学術誌で受理済み、出版待ち | まだ未公開(近日公開予定) | ★★★★★ (査読済みで信頼度高い) | 正式に引用可能 |
| submitted | 学術誌に投稿済み、審査中 | 未公開 | ★★☆☆☆ (未承認のため不確実) | 原則、正式引用不可(preprintとして公開されていれば可能な場合あり) |
| in preparation | 投稿準備中、執筆中 | 未公開 | ★☆☆☆☆ (研究者の自己申告段階) | 引用不可 |
| personal communication | 個人的なやり取りから得た情報 | 未公開(第三者確認不可) | ★★☆☆☆ (信頼は人物依存) | 最小限に限定して引用可(ジャーナルによって規定あり) |
| 通常の論文 | 学術誌で出版済み | 公開済み | ★★★★★ (査読済み・公開済み) | 正式に引用可能 |
※信頼度の⭐︎の数は、あくまで筆者の評価です
ワンポイント解説
- 信頼度トップは「通常の論文」と「in press」。査読を通っているので安心。
- submitted はまだ審査中なので、油断は禁物。
- in preparation は引用できないけれど「今後出る予定」と知るための目安にはなる。
- personal communication は裏付けがとれないので慎重に扱う必要がある。
こうして比較してみると、同じ「参考文献リスト」に並んでいても、情報の重みが大きく違うことがわかります。
論文を読むときには「これはどの段階の情報なのか?」を意識してみると、研究の理解度もグッと深まりますよ。