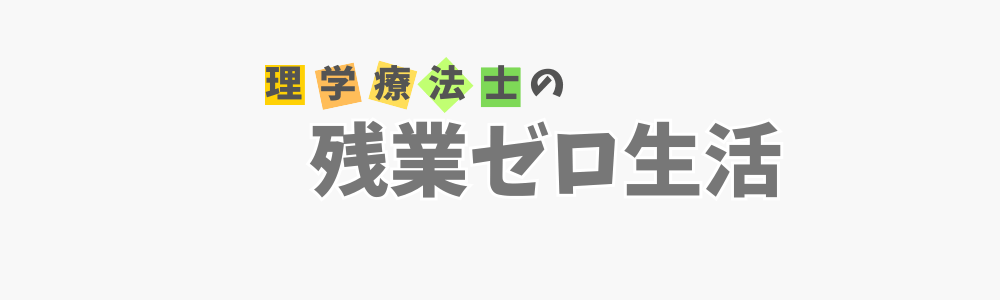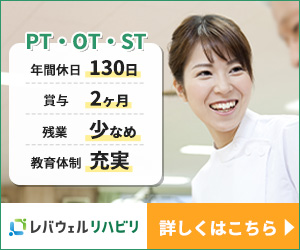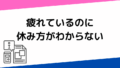理学療法士が年間に起こすインシデント(ヒヤリハット)は大体6.8件と言われています。
安全管理は周辺環境を整えるだけでなく、セラピストの声掛けも非常に重要になってきます。
どのような場面で危険があるのか、例を4つ上げますのでここで復習しましょう。
事故を起こした人は、もう起こさないように。
まだ事故を起こしていない人は、これからも起こしませんように。
安全管理①:訪室したときに気を付ける危険ポイント

まずリハビリをする時は患者さんを部屋に迎えに行きます。
そして、起き上がって靴を履こうとするはずです。
ここがポイントです。
患者さんはこの時、脳内で『リハビリ時間だから起きなきゃ』と考えます。
その為、起き上がって靴を履いたらすぐに歩き出そうとする、もしくは移乗しようとします。
これがヤバい。
この『すぐに』という動作が最も危険なのは周知のとおり。
クルマでも『急ブレーキ』『急ハンドル』は事故の元でしょ?
ここでどのような声掛けをするかであなたの安全管理能力が問われるのです。
十分に評価出来ていて、この患者さんは自立移動しても大丈夫であれば良いのですが、その能力が学生や経験の浅いスタッフでは不十分になりやすいです。
ここで
- 『準備するので座ってお待ちください』
- 『では一緒に行きましょう』
などの声掛けができていればよいです。
転倒事故は自室内でおこりやすく、リハビリ室などではどんなに難しい運動をしても転倒回数はそこまで多くありません。
やはり、自分の慣れている環境での転倒が最も多いということを認識しておくべきです。
もちろん、端坐位保持が困難で倒れそうな患者さんであれば、
すぐ介助に入れるよう隣に位置したり、肩甲骨あたりを支えるなどの対応が必要になります。
このような対応が出来ているでしょうか?
ひやっとした経験が無ければ、肝に銘じておいてください。
【患者は動き始めが最も危険!】
安全管理②:部屋から移動中の危険ポイント

今度は患者さんをリハ室まで移動する時です。
例えば杖歩行であれば、杖の持ち方は適切か(たまに前後逆に持つ方がいる)、周囲の安全に気を配れているかが問題となります。
前方から人が来た時に適切に避けることができるのか、それとも立ち止まって人が通り過ぎるのを待つのか、どちらの対応が患者さんにとって安全でベストな選択なのかをすでに評価し、理解していなければならないのです。
その適切な判断を患者自身ができていない場合、声掛けが必要となります。
この移動時も治療時間として考えると、セラピストはこの時間も患者の行動に目を光らせていなければいけないので、ボーっとしててはいけませんよね。
例えば、人が来ているのにズンズン進もうとする人には
- 『ちょっと止まりましょう』
- 『少し左によりましょうか』
などの声かけが出来ているでしょうか。
しかも可能であれば、その『実際に危険になる少し前』に、我々が判断する必要があります。
患者さんの能力を総合的に判断し、かつ、声かけをするタイミングを誤らないようにしましょう。
あまり声かけをしすぎると、患者さんにとって良い事ではありません。
患者さんは自分で考えて行動しなければならないのです。
患者さんが自らよけたり止まったり、という判断ができるようにならなければ自宅で生活はできませんよね。
『避けるのか止まるのか、患者より先にセラピストが判断すべき!』
安全管理③:リハ室についてすぐの危険ポイント

リハ室に到着しても危険はいっぱいです。
リハ室こそ『安全』とは最もかけ離れているのを知っていないといけません。
プラットホームに移動する際にも危険な場面が多くあります。
しっかりと正面を向いて座ってられるか、着座はゆっくりとできているか、そのような所をしっかりと見極めるのです。
仮に『ドスン』と座ったしまい、『あー、それダメですよ』と言うのは簡単です。
そんなん誰だって分かるからね。
その患者の特徴を理解し、座る前から『着座速度が性急になる可能性があるな』と予測し、『ドスン』と座る前に注意喚起をしましょう。
座る直前に『ゆっくり座りますよ!』と声かけすればいいだけですからね。
特に学生の場合は事故を未然に防がなければならないので、この注意喚起は必要です。
しかし、できていない学生も多いですねー。
何も言わずに『ドスン』と座ってしまった後に、ヤバいという表情をしてオロオロとバイザーをチラッと見てるようじゃだめですよ。
何のためにアナタいるんですか!
学生に最も重要な物は『安全』なので、ここを理解しましょう。
『患者がどんな動作をするか予測し、危機回避しよう』
安全管理④:日常で危険ポイントは沢山!安全を確認する癖をつけよう

今度は日常での危険です。今までは患者の危険でしたが、セラピスト側の危険回避能力も問われます。
例えば
- 車椅子を後方から押しているときにフットレストが壁にぶつからないか。
- エレベーターを使用する際に挟み込みはないか。
- 机に着ける際にアームレストにおいた手を挟まないか。
- ベッドに横になる際、車椅子に足を当てないか。
- 頭を降ろす際に頭をぶつけないか。
- 靴を脱ぐ時に後ろに倒れないか
日常にはたくさんの危険が潜んでいますので、しっかりと予測を立てながら行動しましょう。
患者の危険の多くは、医療従事者側が予測をしっかり立てられて入れば予防できる案件が多いです。
先日も、病室で転倒した患者さんがいましたが、これで3度目だそうです。
患者さんの転倒リスクをしっかりと認識し、対策を立てていればこのような事態にはならなかったでしょう。
1度ならまだしも、同じ患者さんを何度も転倒させるようでは危機管理能力が欠如しているとしか言いようがありませんよね。
『一番の危険は医療従事者の認識不足』
さいごに:安全管理は危険予測がキモとなる
病院では病院独特の危険があります。
それを環境設定でクリアさせていきたいのですが、なかなか難しい場面も多いです。
ですので、セラピストはしっかり危険予測を行い、事故の無いように努めていかなければいけません。
意外とできていない人も多いので、しっかりと理解を深め、安全なリハビリを提供しましょうね。
安全管理は予測から!
ですよ!