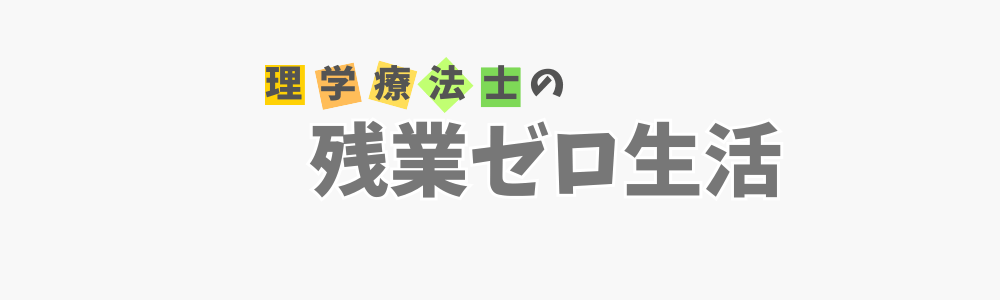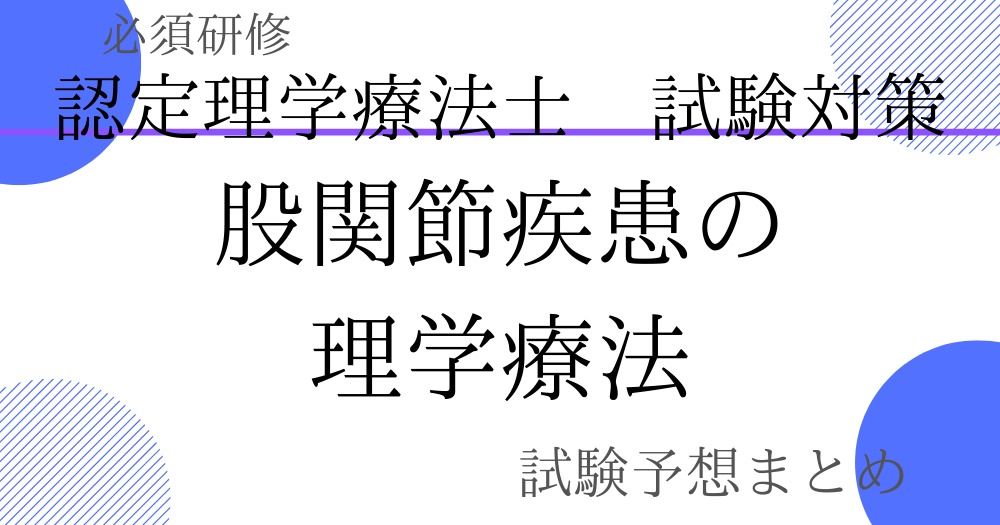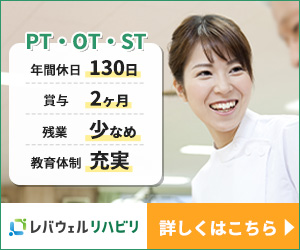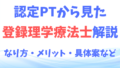「股関節疾患の理学療法って、どこが試験に出やすいの?」
認定理学療法士・必須研修の3コマ目『股関節疾患の理学療法』で重要(試験に出そう)な部分をまとめました。
特に
- ガイドライン
- 解剖構造
- 画像評価
の3つは要チェックです。
<return>
【認定理学療法士試験対策】専門問題テスト:肩関節疾患の理学療法
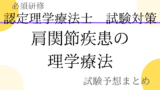
【認定理学療法士試験対策】肩関節疾患の理学療法:運動器の専門問題まとめ②
認定理学療法士試験「運動器専門分野」対策に必須!肩関節疾患(腱板断裂・肩関節周囲炎・不安定症)の理学療法をわかりやすく解説。出題傾向や保存療法・術後リハのポイントまで網羅したまとめ記事です。
股関節の骨構造
- 寛骨は腸骨、坐骨、恥骨から形成される
- 大腿骨には頚体角と前捻角がある
- 解剖学的肢位において、水平面では寛骨臼と大腿骨頭との向きが一致しない
- 真上から見ると前面は骨頭全面が露出しており、後面に比べると骨製の安定性はない
骨盤・寛骨臼の男女差
- 骨盤の上口、下口ともに女性の方が横径は大きい
- 寛骨臼の前捻や、前額面での傾斜、大腿骨の前捻角は女性の方が3-5°程度大きい
股関節の適合局面
- 屈曲・内転・内旋:前方インピンジメント(THAで後方脱臼リスク)
- 伸展・外旋・(・内転):後方インピンジメント(THAでは前方脱臼リスク)
寛骨臼形成不全
寛骨臼形成不全では、健常者よりも荷重を支持する面積が小さく、応力が寛骨臼の外側部に集中しやすい
大腿骨前捻角
- 過前捻に対し、適合を修正すると下肢内戦が生じる
- 前捻角はレントゲンで撮影されることは少なく、MRI、CTの股関節水平断の画像から判断する
- 前捻角の検査にはCraig testを用いる
関節包・靭帯・関節唇
- 腸骨大腿靭帯
- 恥骨大腿靭帯
- 坐骨大腿靭帯
- 輪帯
- 大腿骨頭靭帯
- 寛骨臼横靭帯
関節包・靭帯の機能
- 伸展・外旋:腸骨大腿靭帯で制動
- 伸展・外旋・外転:恥骨大腿靭帯で制動
- 内旋:坐骨大腿靭帯で制動
大腿骨頭より直径の小さい輪帯は大腿骨の牽引負荷に抗して股関節を安定させる
関節唇の機能
関節内を陰圧に保つことによる股関節安定化と関節への圧力の均一化に貢献
神経・血管
<関連痛>
股関節の病変により股関節以外の部位に疼痛を生じる関連痛が起こる。大腿や下腿、足部にまで及ぶことがある。
画像から得られる情報
股関節正面像
下肢伸展、軽度内旋位、膝蓋骨正面で撮影。上前腸骨棘は触診上水平にして撮影
- 前傾:閉鎖孔は小さく細長い。骨盤空は丸く大きい
- 後傾:恥骨結合は長く、閉鎖孔は大きく写る。骨盤空は扁平化し、仙骨と重なる
臼蓋形成不全症の判定基準に関する単純X線計測
- CE角:骨董中心をとおる垂線と寛骨臼外側縁を結ぶ線のなす角度
- Sharp角:左右涙痕下端の接線と涙痕下端と寛骨臼側縁を結ぶ線のなす角度
- AHI:大腿骨内側縁から寛骨臼外側縁までの距離を大腿骨内側縁から外側縁までの距離で除し、百分率で表した値
- 寛骨臼荷重部傾斜角:寛骨臼荷重部(月状面)の内側縁と外側縁を結ぶ水平線とのなす角度
臼蓋形成不全症の判定基準
- CE角:20度以下
- Sharp角:45度以上
- AHI:75%
- 寛骨臼荷重部傾斜角(ARO):15度未満
大腿骨の回旋を画像で評価
- 小転子が左右対象でない場合:小転子が小さい→内旋傾向 小転子が大きい→外旋傾向
・腸骨の正面性は合っているか? - 上前腸骨棘と仙腸棘の距離が左右対称であれば正面を向いている
どちらかが短ければ、短い方に回旋している
変形性股関節症の骨棘
- Roof
- 上頸部骨肥厚
- 象鼻
- 下頸部肥厚
- Floor
- Double Floor
- Capital drop
股関節周囲筋の運動学
筋力=筋張力×モーメントアーム
筋長およびモーメントアームの変化により
- 股関節伸展位や深屈曲位では大腿直筋や縫工筋より腸腰筋の発揮トルクが相対的に優位になる
- 股関節伸展位ではハムストリングスに対して大殿筋の発揮トルクが相対的に優位になる
股関節深層筋の機能
- 緊張力により骨頭を安定させる
- 関節包の緊張を介して骨頭を誘導する
- 感覚器として機能する
- 遅筋線維の割合が高い
- 筋紡錘の密度が高い
内転筋
内転筋の多くは
- 股関節屈曲0度で屈曲作用
- 股関節屈曲90度で伸展作用
を有する
トルクと張力
発揮されている筋トルクは同じでも緊張力バランスが悪化すると関節に加わる負荷に影響を及ぼす
股関節と隣接関節の関連性
Coxitis knee
変形性股関節症と膝関節痛、変形性膝関節症との関連は多く報告されている
代表的なCoxitis kneeの下肢アライメント異常
<左変形性股関節症の場合>
- 対側内反膝変形、患側外販膝変形(右膝<の字、左膝<の字)
- 対側内反膝変形(右膝<の字、左膝Iの字)
- 対側外反膝変形(右膝>の字、左膝Iの字)
- 両側外反膝変形(右膝>の字、左膝<の字)
骨盤回旋と股関節への応力
- 骨盤前傾:寛骨臼の骨頭被覆は増加し、単位面積あたりの応力は減少する
- 骨盤後傾:寛骨臼の骨頭被覆は減少し、単位面積あたりの応力は増加する
股関節疾患に対する理学療法
ガイドライン2017
運動強度(strengthening&endurance exercise)
グレードA
- 個別の柔軟性、筋力、持久力改善運動を用いるべき
- グループでの運動療法は対象の最も重要な問題に対処するための運動を処方するべき
- 頻度と強度は、軽度から中等度の患者に1~5回/週、6~12週実施すべき
患者教育(patient education)
グレードB
- 患者教育を運動療法や徒手療法と合わせて提供すべき
- 患者教育は活動の変容、運動療法、過体重にたいしては減量方法、関節変の関節の負荷軽減などを含むべき
論理的手法(modalities)
グレードB
- 運動療法やホットパックに加え、股関節の前、後、側面への超音波(1MHz、1w/cm2、5分間)を2週間で10回行ってよい
徒手療法(manual therapy)
グレードA
- 軽度から中等度の患者に対し、可動域制限や柔軟性低下、疼痛に対して徒手的療法を用いるべき
- 頻度と期間は1~3回/週、6~12週間は実施すべき
- 股関節の動き改善につれて、可動域制限や柔軟性低下、疼痛を維持・改善するためにストレッチングや筋力強化運動を加えていくべき
変形性股関節症診療ガイドライン2016
変形性股関節症に対する運動療法の効果
グレードB
- 運動療法は、短・中期的な疼痛の緩和、機能改善に有効
- 長期的な病気進行に関しては不明
THAにリハビリテーションの有効性
グレードB
- THAの術前、術後リハビリテーションは、歩行、筋力、可動域および心理状態の向上に有用
変形性股関節症に対する歩行補助具、装具の効果
グレードB
- 歩行補助具(杖・歩行器)は疼痛緩和に有用であるが長期的な病気進行予防に関しては不明
変形性股関節症に対する患者教育の効果
グレードA
- 変形性股関節症に対する患者教育は、病識の向上などに有用で行うべきである
グレードB
- 患者教育に運動療法などを併用することで症状の緩和が期待できる
まとめ(試験後の追記)
「股関節の理学療法」の範囲では解剖学とガイドラインが重要となっています。
股関節の運動学は出題されなかったように記憶しています。
ガイドライン2017と2016は非常に重要ですので、ぜひ覚えておきましょう!
<next>
【認定理学療法士試験対策】専門問題テスト:理学療法ガイドライン



【認定理学療法士試験対策】理学療法ガイドライン:運動器の専門問題まとめ④
認定理学療法士試験に頻出の「理学療法ガイドライン第1版(2011)」から、変形性膝関節症に関する推奨グレードとエビデンスレベルを整理。試験で狙われるA項目を中心に効率よく復習できます。