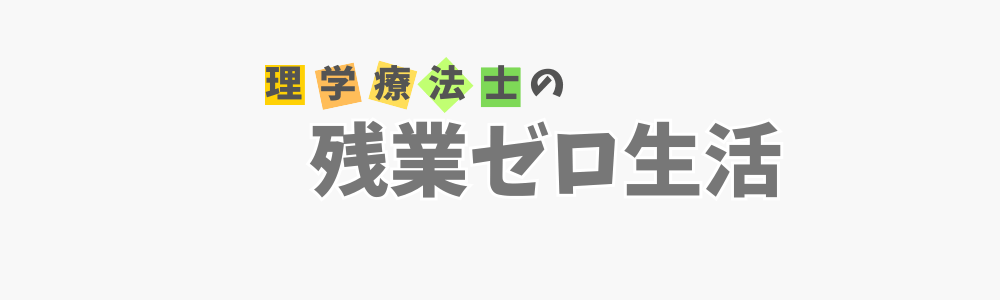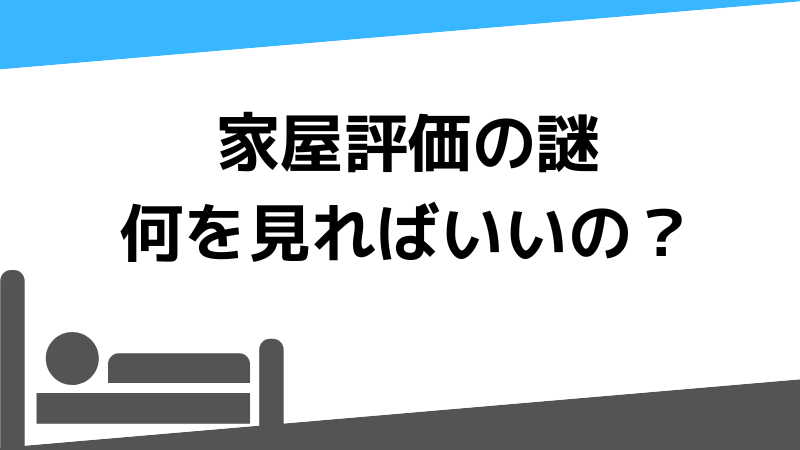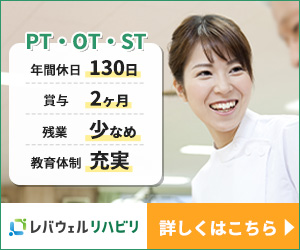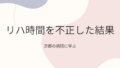回復期リハビリテーションでは、患者さんの治療をする事も目的の一つですが、それ以上に重要な任務があります。
それは、患者さんを在宅復帰させる、ということです。
患者さんを安全に自宅に帰すために実施しておかなければならない事の一つが家屋評価です。
身体機能が向上しても、家屋構造によっては在宅復帰できない場合もあります。
そうならないために、しっかりと家屋状況を把握し、安全に患者さんが自宅に帰れるように手助けしなければなりません。
在宅復帰に重要な家屋評価
家屋評価とは、その患者さんが家に帰っても安全に生活できるかを調査する仕事です。
- セラピスト
- ケースワーカー
- ケアマネ
- 福祉用具の担当
が一斉に自宅に上がり、生活できるかを検証します。
こう書くとなんだか物々しい状況を想像しますが、比較的穏やかに事が進むことが多いです。
家族もその患者さんを受け入れる気持ちがあるわけですからね。
家屋評価を実施する目的は、『患者さんが安全に生活できる環境を作る』と同時に『家族が安心して生活できる状況を作る』という目的も達成しなければなりません。
患者さんが帰った瞬間から、家族や患者さんが肩身の狭い思いをするのでは問題ですからね。
つまり、患者目線でなく、家族目線でのアドバイスが必要になってきます。
家屋評価で見るポイントと福祉用具の選択
家屋評価は
- 『自宅への出入り』
- 『自室ベッドの配置』
- 『トイレへの動線・トイレ動作』
- 『浴室への動線・入浴動作』
- 『危険物(転倒など)の撤去』
- 『社会保障サービスを勧める』
という項目を確実に実施しなければいけません。
その項目を一通り患者さんに実施して頂いたり、専門家に話をしてもらい、徐々に家での生活イメージを膨らませていきます。
そして、家屋構造も調査し、そのままの構造で患者さんや家族は生活できるのか?手すりや椅子などの設置が必要なのか?住宅改修が必要なのか?などを検討していきます。
家屋評価において、提供する福祉用具トップ3は
- 『介護ベッド』
- 『シャワーチェア』
- 『簡易手すり』
となります。
電動ベッドの選び方
電動ベッドは昇降式の物を選びます。
- 1モーター:頭の挙上
- 2モーター:頭の挙上とベッドの昇降
- 3モーター:頭の挙上とベッドの挙上と足の挙上
その患者さんの障害に合ったものを選びましょう。
足だけ上げることのできる3モーターは、下肢のむくみが酷かったり、循環障害がなければ選ぶ必要はないので、基本的には2モーターを選ぶことになるでしょう。
モーター式ベッドは、普通のベッドより大きいですし、遥かに重たいです。
スペースや床材の状況もきちんと確認しておきましょう。
特に畳の部屋に置く場合は、畳の沈み込みに十分注意しなければなりません。
場合によっては、床材などの変更を提案します。
最近はホームセンターやインターネットで、和室をフローリングにできるカーペットがあるので、それを使用しても良いでしょう。
シャワーチェアの選びかた
シャワーチェアは衛生用品ですので、レンタルはなく、購入となります。
お風呂の広さや、扉の開閉様式などを考慮し、サイズを選びましょう。
折り畳み式の物選ぶのが一般的です。
手すりの選び方
簡易手すりは置き型の物と固定型のものがあります。
置き型のものは重量が20kg前後ありますので、非常に重たいです。
それを椅子の隣やベッド周囲に置いて、手すりにするもので、壁に穴を開けなくて良いので賃貸住宅などで重宝します。
【置き型手すり】
固定型のものは、突っ張り棒のようなものを想像していただけると良いです。
天井と床で固定し、縦手すりにします。
これは、天井の素材が強固でなければつけることができません。梁などに固定することが多いのですが、場所を選んでつける必要があります。
主に玄関などに使用することが多いですね。
そして、固定型で最も固定力があるのが、壁にビスで止めるタイプです。
耐荷重はかなり強く、物によっては5.0kN(約50kg重)程度に耐えるものもあります。
【手すり画像】
最近の住宅は良い事ばかりではない?特徴を抑えよう
最近の住宅は、昔の住宅と比べて変化しています。
例えば、バリアフリー化。
部屋ごと敷居を無くし、全くフラットに、段差があっても3cm以下というものが多いです。
そして、玄関の上がり框。
古い住宅ではこの框が40cm前後ある場合が多かったですが、現在は20cm前後となっています。
これは土間がなくなり、家の外に段差を設けることで上がり框を無くす方向になっているからです。
浴室は保温性の高い柔らかい床、滑りにくい床になり、浴槽も昔は60cm以上の高さがあったのですが、最近では40cm程度のユニットバスが主流となっていますよね。
寝転ぶように入る浴槽もあり、浴槽事態も真四角ではなく緩やかな曲線で描かれているものも多いですね。
この、住宅業者が良かれと思って進化させた部分、実は患者さんにとって非常に生活しにくくなっているのです。
まず段差。段差は全くないに越したことはないのですが、段差が1cmとか2cmある場合。
これがまずい。
通常、段差は低ければ低いほどいいはずなのですが、患者さんにそれは当てはまりません。
段差が低すぎて段差の有無を認識できず、その僅かな段差に躓いてしまうことが非常に多いです。
むしろ、昔の住宅のように5cm以上の段差があったほうが認識できるので、安全なことが多いです。
もし1cm前後の段差がある場合は、段差解消スロープで段差を無くしましょう。
【段差解消】
身体的不自由がある、高齢者のお宅にも積極的に取り入れていきたい物品ですね。
上がり框は、靴を履くのに重要な役割を果たしていました。
昔の住宅のように40cm程度であれば普通の椅子と同じ高さですから、そこに腰かけて靴を履いたりできていました。
しかし、その框が最近の住宅のように20cm程度になると、患者さんは20cmの段差に座って靴を履くか、立って履くしかありません。
20cm台から立てる患者さんはそうそういませんよ。
ですので、玄関には靴を履く用の椅子やベンチを設置しなければならなくなります。
玄関は広く取りたい所なのに、その椅子のせいで狭くなってしまいます。
浴室では、浴槽や床面に滑り止め加工がしてあるので、吸盤が付きにくくなっています。
浴槽の中に小さな椅子を沈め、吸盤で固定させるタイプは上手く張り付かず、浮いてきてしまうこともあります。
また、曲線で作られた浴槽は、クリップと言われる挟み込み手すりが設置できません。
したがって、浴室内で手すりを確保するのが非常に困難になってしまいます。
まとめ:PTは不動産屋に近い知識も必要!
家屋評価はその人たちの生活を我々が守る為に実施するものです。
ですので、たくさん福祉用具を入れれば良いというものではないですし、サービスも使い放題という訳でもありません。
そこには部屋の空間や家族の生活動線、予算(コスト)という側面が発生します。
いかにスムーズに退院後の生活が送れるか、それを考えながら評価していきます。ですので、最近の住宅事情も知っておかなければなりません。
家屋図を確認し、ここに手すりを付ければいいかな?と、考えて、実際に家に向かったらスペース不足で全く付けられなかったなんてことはざらにあります。
ぜひ、あらゆる予測を立てておき、対処法も1つでなく、最低でも2つは用意して家屋評価に臨みましょう。
今、あなたが住んでいる家で、車椅子で生活できますか?
おそらく大半が出来ない(もしくはしにくい)と感じるはずです。
それを何とかして、患者さんと家族の平穏で安全な生活をフォローするのが家屋評価の目的なのです。
【家屋について学ぼう!】