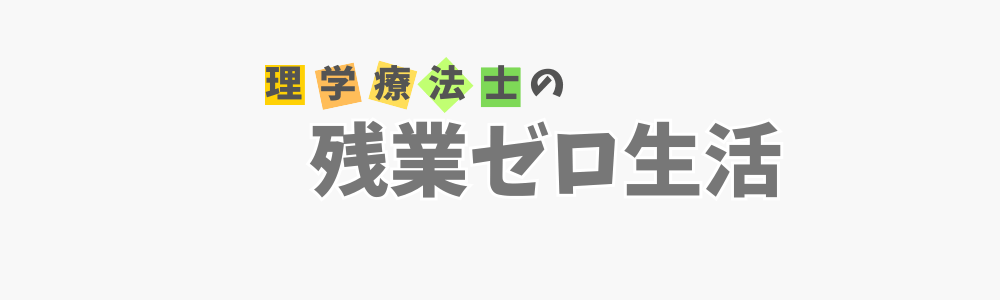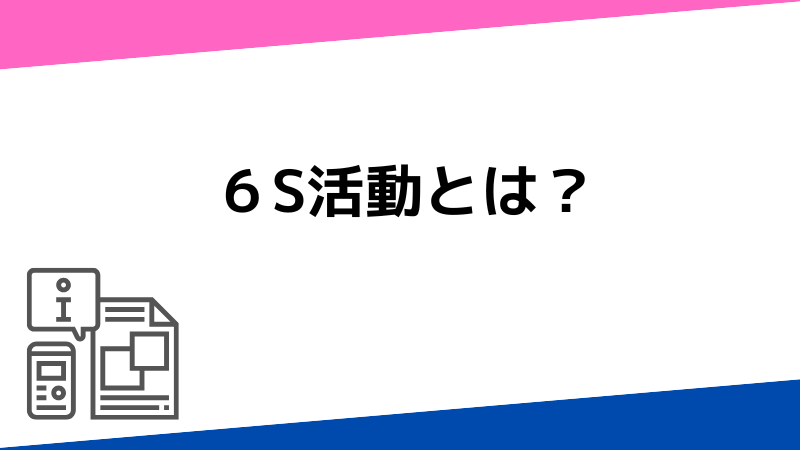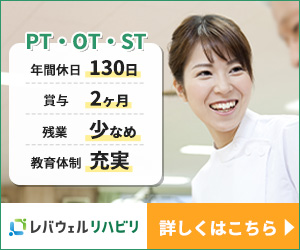6S活動とは?5Sとの違いを徹底解説
「職場がきれいに整っている人は仕事ができる」——この言葉は多くのビジネス現場で耳にするフレーズです。実際に成果を出している人や、生産性の高い職場は、机や作業環境が整理され、効率的に仕事を進めています。その背景にあるのが 6S活動 です。
一般的に知られるのは「5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」ですが、医療や介護、サービス業ではさらに 作法(Saho) を加えた 6S活動 が導入されています。これにより、物理的な環境改善だけでなく、従業員の態度やマナーも含めた トータルの業務改善 が可能になります。
6S活動の6つの要素と目的
6S活動は以下の6つの要素で構成され、どれも職場改善に欠かせない重要な役割を持っています。
①整理(Seiri)〜必要なものだけ残す
整理は 要る物と要らない物を区別し、不要なものを処分すること を指します。
-
不要な物を取り除くことで、机や棚がすっきりし、作業効率が向上します。
-
医療現場では、古い医療器具や期限切れの薬品を整理することで、患者に安全で安心な環境を提供できます。
-
例:ある病院では、倉庫に眠っていた不要機器を整理・廃棄した結果、年間で約20時間分の探し物時間を削減できた事例があります。
ポイント:整理は「捨てる勇気」が重要。必要なものだけを残すことで、作業効率や安全性が大幅に向上します。
②整頓(Seiton)〜必要なものをすぐに取り出せる配置に
整頓は 必要なものを決まった場所に置き、誰でもすぐに取り出せる状態にすること です。
-
「見える化」やラベル管理を徹底することで、作業の迷いを減らします。
-
工場や医療現場では、部品や医療機器の配置を色分けラベルや棚番号で管理する事例があります。
-
例:ある工場では部品棚に色別ラベルを導入しただけで、部品ピッキング時間が30%短縮されました。
ポイント:整頓は「すぐに見つけられる」ことが基本。効率化だけでなく、安全性の向上にも直結します。
③清掃(Seiso)〜清潔な環境を作る
清掃は単なるゴミや汚れの除去ではなく、汚れる原因を取り除くこと も含まれます。
-
毎日の簡単な清掃ルールを作ることで、職場環境の快適さを維持。
-
医療現場では、PC周辺機器や診療用具の清掃が故障防止や感染予防につながります。
-
例:あるオフィスでは、毎日10分の清掃ルールを徹底することで、PCや周辺機器の故障率が2割減少しました。
ポイント:清掃は「習慣化」が大事。原因を排除することで、トラブルを未然に防ぎます。
④清潔(Seiketsu)〜整理・整頓・清掃を維持する
清潔は、整理・整頓・清掃を継続的に維持することです。
-
机や備品、制服などを常に清潔に保つことで、誰が使っても快適な状態を作れます。
-
医療や介護の現場では、患者や利用者に安心感を与える重要な要素です。
-
例:ある介護施設では、制服を常に清潔に保つルールを導入したところ、利用者からの信頼度が大幅に向上しました。
ポイント:清潔は「維持すること」が目的。物理的な整理だけでなく、心理的な安心感にも直結します。
⑤躾(Shitsuke)〜ルール・規律の習慣化
躾は職場のルールや規律を守る習慣化を指します。
-
定期的な研修や上司の指導力、教育制度の整備も躾の一環です。
-
これにより、組織全体のモラル向上やヒューマンエラー防止につながります。
-
例:整形外科クリニックでは、新人研修に6S活動を取り入れたことで離職率が低下した事例があります。
ポイント:躾は「習慣化」がキーワード。ルールを守る文化が職場全体に広がります。
⑥作法(Saho)〜礼儀作法・態度・言葉遣い
作法は、患者・顧客対応における礼儀作法や態度、言葉遣いを習慣化することです。
-
「お辞儀・挨拶マニュアル」を導入することで、サービス品質や顧客満足度の向上が期待できます。
-
医療現場では、患者への接遇マナーとして重要視されています。
-
例:ある企業では、作法の徹底で顧客満足度が10%以上向上しました。
ポイント:作法は「人に見せる環境づくり」。信頼や安心感を高める要素です。
6S活動を導入するメリット
6S活動は単なる「掃除活動」ではありません。実施することで以下のメリットがあります。
-
業務効率化:探す・迷う時間を削減
-
残業削減:定時内で作業完了
-
コストカット:残業代、電気代、備品ロスを削減
-
社員満足度アップ:快適な職場でストレス軽減
-
サービス品質向上:作法・マナー向上で顧客満足度アップ
-
安全性向上:事故・ヒューマンエラー予防
特に医療・介護現場では、患者や利用者に 安心感・信頼感を与える効果 が大きく、企業や教育機関、公共施設でも導入が進んでいます。
6S活動の具体的な進め方と事例
ステップ1:整理
-
「捨てる勇気」を持つ
-
例:倉庫の不要機器を廃棄し、年間20時間分の探し物時間を削減
ステップ2:整頓
-
「誰が見ても分かる配置」を徹底
-
例:部品棚に色別ラベルを導入し、作業時間30%短縮
ステップ3:清掃
-
毎日10分の清掃ルール
-
例:PC周辺の清掃で故障率2割減少
ステップ4:清潔
-
「新品の状態」を維持
-
例:介護施設で制服の清潔を維持し、利用者からの信頼度向上
ステップ5:躾
-
定期的な研修・教育の実施
-
例:整形外科で新人研修に6Sを導入し離職率低下
ステップ6:作法
-
患者・顧客対応の言葉遣いや立ち居振る舞いを徹底
-
例:挨拶マニュアル導入で顧客満足度10%向上
6S活動を習慣化させるコツ
6S活動は 一度やったら終わりではなく、習慣化が鍵 です。
-
ルールを明文化(チェックリスト化)
-
見える化ツールの活用(ラベル、掲示板、アプリ)
-
小さな改善を積み重ねる(毎日5分の活動から)
-
成功事例を共有(チームでモチベーション維持)
多くの職場では、6Sが定着すると自然に 「7S=習慣」 が身につくとされています。
6S活動は仕事だけでなくプライベートにも効果あり
6Sは職場改善だけでなく、日常生活にも応用できます。
-
家庭の整理整頓 → 時間短縮&ストレス軽減
-
キッチン整理整頓 → 料理効率アップ
-
礼儀作法の習慣化 → 家族や友人との人間関係改善
つまり、6S活動は 人生全体の質を高める行動習慣 なのです。
まとめ:6S活動で業務改善と人生改善を実現
6S活動は単なる掃除や整理整頓にとどまらず、
-
環境の整備
-
業務効率化
-
モラル・マナー向上
-
人生の質改善
といった多方面の効果をもたらします。
医療現場や企業だけでなく、家庭や日常生活に取り入れることで、無駄がなく、効率的で、美しい仕事と生活 が実現できます。
「まずは整理から」——今日から一歩ずつ、6S活動を習慣化してみてください。